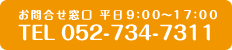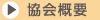| 一般社団法人『NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会』の招待会員にお迎えいただきありがとうございます。 設立以来、積極的に様々な方面への働きかけを進めておられることに、心より感謝いたします。 私たちの暮らしに欠かせない存在である紙おむつは一方で大量に発生するゴミの問題を抱えています。消費者としてできることに一つずつ取組みながら、課題解決を図っていきたいと思っています。時間はかかりますが、全国の加盟団体でも様々な機会をとらえて情報を共有してまいります。動きだしている地域からの発信も大切です。これからも力をあわせて頑張っていきましょう。 貴推進協会のますますの御発展をお祈りしています。 |
|
全国地域婦人団体連絡協議会 会長 岩田 繁子 |
|
 |
|
| 紙おむつのリサイクルについて考えた方が良い!と初めて考えてから10年の時が過ぎました。その当時、3人のわが子の子育てに紙おむつには非常に世話になっているところでした。また、仕事上、廃棄物の適正処理について様々な調査研究をしていましたが、使用済紙おむつをリサイクルするといった発想は、まったくありませんでした。 考え方が変わったきっかけは、平成19年から2年間、埼玉県で実施した「埼玉県事業系ごみ削減対策事業」でした。ごみ削減=リサイクルの推進であることから、排出事業者が分別しているにもかかわらず、混合収集されるごみに着目して調査を実施しました。使用済紙おむつは、分別されているにもかかわらず調査対象から外しました。理由は、リサイクル先がないためです。パッカー車を開けるたびに“ドサドサ”と重い音をたて落ちるたくさんの袋を見ながらどうにかならないものか!と考えたことを思い出します。現在も、県内の状況は全く変わっていません。車窓から街を見ていると、むしろ排出事業所は増えているように感じます。 使用済紙おむつのリサイクルを進展するには、紙おむつは技術的かつ経済的にリサイクルできるという、啓発及びリサイクルシステムの構築が必要です。そのためには、貴推進協会の役割が非常に重要になると考えています。今後、益々の発展を期待しています。 |
 埼玉県環境科学国際センター 資源循環・廃棄物担当 主任研究員 川嵜 幹生 |
 |
|
| 日置市は、2012年度から生ごみリサイクル事業をはじめとした、多種多様で持続可能な脱炭素社会に向けての取組を行っており、加えて令和3年9月30日には、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現(ゼロカーボンシティ)を目指すことを宣言しました。 廃棄物の焼却などにより、発生するCO2を抑制するには、紙おむつのリサイクルも積極的に取組む必要があると考えており、行政として、資源化の方向性を考え将来的に有効活用できるよう、会員の皆様と協働しながら地球環境に優しい「ゼロカーボンシティひおき」を目指してまいります。 |
 日置市 市長 永山 由高 |
 |
|
| 高齢者介護が中心の当法人の入所ベッドは1,000を超える。脱おむつの排泄ケアにカを入れつつも、毎日の使用済み紙おむつを「廃棄物」として処理していることに心を痛めている。 尊厳あるケアを標榜するからには、廃棄物としてではなく、再生可能なものにできないかという永年の強い思いをもっていた。技術的な課題や環境関連法などとの兼ね合いで一筋縄ではいかないとも仄聞している。全ての関係者が同じベクトルでなければ進展はないだろう。 発足した「一般社団法人NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会」が中心となって「使用済み紙おむつの再生」という夢の実現を期待している。 |
 社会福祉法人 渓仁会 理事長 谷内 好 |
 |
|
| この度は、一般社団法人『NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会』の設立、誠におめでとうございます。 私が紙おむつリサイクルのことを知ったのは、テレビ番組でした。使用済み紙おむつを熱源に換えられるというところに惹かれました。 紙おむつの燃料化リサイクルは、300kgの紙おむつから約100kgのペレット燃料ができます。それを介護施設のお風呂などに活用すれば燃料代とごみを削減できると期待しています。 資源循環が完全にできるのが実にすばらしい、もし当施設の利用者がこのシステムのことを知ったらきっと喜ぶでしょう。 私は誰もやらないことに挑戦してきました。長い冬、外で遊ぶ時間の少ない新潟の子どもに体力をつけさせたくて造った保育所の温水プールは社会福祉法人初のことでした。前例がないからやらないのはやる気がないからです。紙おむつのリサイクルは誰かがやらなければならないと考えています。 一般社団法人『NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会』のご発展に協力させて頂き、紙おむつリサイクルの実現に向けて共に歩んでいきたいと思います。 |
 社会福祉法人 勇樹会 理事長 中野 勇 |
 |
|
| 弊社トンネルコンポスト方式の処理技術は、2004年頃に親会社であるエビス紙料の先代社長がヨーロッパで出会った高速堆肥化技術が基礎となり、燃えるごみを焼却せずに微生物分解により石炭代替燃料に変える技術です。エビス紙料は創業以来、製紙会社様と大きな関わりを持っており、先代社長は兼ねてより紙オムツや衛生製品などのリサイクルをしたいと考えておりました。ある時、この技術を適用し可燃ごみを固形燃料にすることを思い付きました。そんな中、『ごみは資源』との理念を提唱された初代三豊市長様とのご意向が重なり、香川県三豊市にて世界で初めてのトンネルコンポスト方式による可燃ごみから石炭代替燃料が製造されることになりました。
今後も我々は先代社長や初代三豊市長様の意志を引継ぎ、『ごみは資源』との企業理念を掲げ、新たな資源循環経済の幕開けの一助を担えるよう尽力して参ります。ご指導並びにご鞭撻を頂戴出来ますと幸甚に存じます。 |
 株式会社エコマスター 代表取締役 見澤 直人 |
 |
|
| 紙おむつは社会生活を送るうえで必要不可欠なものとなっております。我々人間のみならず一緒に暮らすペットたちにも紙おむつが必需品であり、それゆえに年々発生量増え続け現在においては60万tを超える紙おむつが国内で消費され240万t近くの紙おむつが処理されております。し尿を吸収することにより約4倍の重量となるわけですがその処理方法については循環型社会を形成する上で非常に大きな役割を担っていると考えております。我々が香川県三豊市で行っている好気性発酵乾燥方式は家庭系、事業系の一般廃棄物をバイオトンネルで17日間発酵乾燥させ固形燃料の原料を生成しております。その技術が貴協会において少しでもお役に立てればと考えており、今後も貴協会とともに紙おむつのリサイクルを通じてSDGsの達成に向け邁進してまいります。 |  株式会社エコマスター 代表取締役 川崎 佳日出 |
 |
|
| 全国的な高齢化社会の進展に伴い、使用済紙おむつの排出が今後も増加することが予想され、焼却ごみの約5%を占めるともいわれております。また、本町においては、岩手医科大学附属病院の令和元年9月移転開院により医療体制が充実した反面、さらなる紙おむつの増加が見込まれます。 私は「ごみは分別(ぶんべつ)人は分別(ふんべつ)」をモットーに、ごみの減量化・資源化が人の心の豊かさを育むものとして、日頃から町政運営はもとより人材育成にも取り組んでおります。 紙おむつの再資源化に向けて一般社団法人NIPPON紙おむつリサイクル推進協会と連携を図りながら、地球温暖化の抑制をはじめ、持続可能な社会の構築(SDGs)に努めてまいります。 |
 矢巾町 町長 高橋 昌造 |
 |
|
| 社会の成熟とともに、乳幼児ケアや高齢者のヘルスケアがますます重要となるのは言うまでもなく、それを支える紙おむつの役割も重みを増しつつあります。 産業としても2030年には世界で10兆円規模に成長する一方、利用後の対応を受け入れざるを得ない自治体等の負担も重くなっている状況は、社会全体の知恵と行動で変えていかなければならないでしょう。 プラスチックのリサイクル、木材などの自然資本の適切な活用、地域循環共生圏の発展、ヘルステック、ベビーテック、エイジテックの創出など、一日も早く対応しなければならない課題や未来を拓く課題が、紙おむつには凝縮されていると言っても過言ではないと思っています。 当推進協会の活動から始まる取り組みが国内のみならず世界にも発信され、最先端のロールモデルとなることを期待しています。 |
 名古屋大学 大学院 工学研究科 化学システム工学専攻 准教授 小林 敬幸 |
 |
|
| 近年の急速な高齢化社会の進行、高齢者の増加により、今後、紙おむつの需要は増加し、使用済紙おむつの排出量は増加することが予想されます。 南伊豆町では、現在、使用済紙おむつは可燃ごみとして焼却処理されており、ごみの減量化やリサイクルの推進をしていく中で、使用済紙おむつのリサイクルは、喫緊の課題であると考えています。 今後の課題解決に向け、使用済紙おむつの効率的・経済的なリサイクルの確立を目指し、一般社団法人NIPPON紙おむつリサイクル推進協会様のご協力をいただきながら、持続可能な社会の構築を目指してまいります。 |
 南伊豆町 町長 岡部 克仁 |